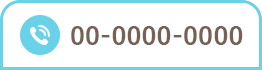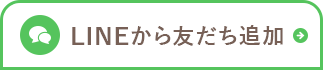小児で下痢・嘔吐を生じる最も頻度の高い疾患は、集団生活で広がりやすい感染性胃腸炎(主にウィルス性)です。激しい腹痛を伴う場合は、腸重積や虫垂炎などの可能性もあり、注意が必要です。嘔吐だけの場合は、便秘や宿便が原因であることが、お子様ではよく見られます。
子どもの下痢・嘔吐
感染性胃腸炎(ウィルス性、細菌性)による下痢と嘔吐は、どちらかだけ現れることもありますが、両方の症状を起こすこともよくあります。感染によって腸管に炎症が生じると腸粘膜からの水分の再吸収が不十分となり下痢が生じます。さらに腸内細菌叢が変化し、腸管蠕動の亢進が起きると下痢に、腸管蠕動の低下が起きると口にしたものが先に進まず胃内に貯留する一方となり嘔吐につながります。
子どもの下痢や嘔吐は、冷えや食べ過ぎ、何らかのストレス刺激など日常的な原因で起こることもあります。また、乳児期は、食道と胃の位置関係が逆流しやすい構造になっており、腹圧や胃内圧が少し上昇するだけでも嘔吐しやすい傾向にあります。
下痢があっても水分摂取が少しずつでき、排尿がある程度得られるようであれば、心配はありません。水分摂取ができずに排尿が全くないときは、脱水症が疑われ、速やかに水分を補充する必要があります。また、経口摂取が極めて少ない状況では低血糖にも注意が必要です。これらの場合は、少量で効率的に水分や電解質、糖分を摂取できる経口補水液がおすすめです。
嘔気が強くて水分摂取ができない場合は、制吐剤(吐き気どめ)を使って水分を摂取できるようにしましょう。脱水傾向のお子様は、コップのまま持たせると一気に飲んでしまうかもしれません。胃腸の動きが悪い状態で大量の水分が入ると、胃内に貯留するだけで先に進まず、何らかの腹圧上昇をきっかけに嘔吐してしまい、十分な水分が体内に吸収されないことになってしまいます。これを避けるためには、5分毎に少量の水分(乳児でティースプーン1杯程度など)を与え、30分程度しても嘔気なく飲めそうであれば、少しずつ量を増やすのが良いでしょう。
子どもの場合、嘔吐と下痢があると脱水症状が進行しやすくなりますので、慎重に状態を観察しましょう。
子どもの下痢について

下痢は、冷えや食べ過ぎ、ストレスなど日常的な原因によって生じる事が多いですが、アレルギー、細菌やウイルスによる感染症など疾患の症状として起こっていることもあります。
感染症の症状として生じている下痢は、増殖した病原体や病原体によって作り出された毒素を速やかに排出するという重要な役割を担っています。そのため、自己判断で市販の下痢止めを服用することは、症状を悪化させたり遷延させることにつながるのでやめましょう。
下痢は、病原体や毒素の排出を促進するために腸蠕動(収縮)が活発に起こった結果であり、多くの場合は腹痛を伴います。お腹を温めたり、マッサージをするなどして、安心させてあげてください。
子どもの下痢のチェックポイント
特に、下記のような症状を伴う場合は、速やかに受診しましょう。
- 元気がない
- だるそうにしている
- ぐったりしている
- 発熱がある
- おしっこが出ない
- 排尿回数が少ない・量が少ない
- おしっこの色が濃い
- 血便がある
- 白っぽい便が出る
- 便の臭いが普段と異なる
- 下痢が続いて改善しない
- 嘔吐する
- 水分を十分に補給できていない
- 睡眠できていない
- 日中に眠たい様子がある
- 目が落ちくぼむ、目の下にくまがある
- 音や光に過敏になる
- 口の中が乾燥している
- 安心させても強い腹痛が続く など
下痢症状がある場合は、お子様の状態や様子を観察し、便の状態や排便の頻度などの症状の内容、発熱など他の症状の有無と内容、機嫌や様子、症状の変化と経緯などを把握し、受診の際に医師へお伝えください。
市販の下痢止めは安易に使用しないようにしましょう
感染症による下痢に対して、下痢止めを内服すると病原体や毒素が体内に長く停滞することにつながり、症状が遷延したり、重篤になってしまう危険性があります。感染症による下痢は病原体や毒素を速やかに体外へ排出するための防御反応であり、自己判断で市販の下痢止めを使用しないようにし、下痢で失われる水分を積極的に補うようにしましょう。それでも下痢止めの服用を検討するほどに心配な時は、診察のうえ、適切なお薬の処方を受けるようにしましょう。
子どもの嘔吐について
 子どもは成長過程にあり消化器の機能も未熟なことから、食べ過ぎなど軽い刺激によって嘔吐することも多いです。赤ちゃんは、胃の構造上、激しく泣いたり、咳き込んだりしたはずみに、腹圧の上昇とともに嘔吐することもあります。また、発熱時には消化管の動きが悪くなり、飲食したものが胃内に停滞しやすく嘔吐しやすくなるお子様も少なくありません。ほとんどの場合は心配がない一方で、嘔吐は腸閉塞や腸重積といった深刻な消化器疾患や髄膜炎など、一刻も早く適切な治療が必要な疾患の症状として現れている可能性もあります。また、頭を強く打った際にも嘔吐症状が起こることがあり、特に吐き気や嘔吐の症状を繰り返す場合は速やかに救急医療機関を受診する必要があります。
子どもは成長過程にあり消化器の機能も未熟なことから、食べ過ぎなど軽い刺激によって嘔吐することも多いです。赤ちゃんは、胃の構造上、激しく泣いたり、咳き込んだりしたはずみに、腹圧の上昇とともに嘔吐することもあります。また、発熱時には消化管の動きが悪くなり、飲食したものが胃内に停滞しやすく嘔吐しやすくなるお子様も少なくありません。ほとんどの場合は心配がない一方で、嘔吐は腸閉塞や腸重積といった深刻な消化器疾患や髄膜炎など、一刻も早く適切な治療が必要な疾患の症状として現れている可能性もあります。また、頭を強く打った際にも嘔吐症状が起こることがあり、特に吐き気や嘔吐の症状を繰り返す場合は速やかに救急医療機関を受診する必要があります。
嘔吐が続くと、身体の水分が失われる一方となり、水分補給が十分にできずに脱水症状を起こしやすくなります。子どもは、成人よりも体内水分量が多く、腎機能の未熟性による水分量の調節が未発達であることや、不感蒸泄(汗など)が多いことなどから、脱水が進行しやすいため、短時間で危険な状態になるケースがあります。ご家庭では、排尿の有無がわかりやすい指標になりますので、注意して観察しましょう。また、脱水の悪循環に陥ると、脱水症状の一つとして嘔吐することもあります。
もし嘔吐した後の機嫌がよく、元気がある場合は、少しずつ水分補給を行いつつ、排尿の有無を観察するようにしましょう。排尿が十分か否か心配な時は、受診のうえご相談ください。
機能性消化管疾患 functional gastrointestinal disorders: FGID
頻回に腹痛を訴えるお子様の中には、検査などで異常がないにもかかわらず、繰り返して悩まれているお子様もいらっしゃいます。
国際的な基準であるRomeⅣ分類において、腹痛を中心とする消化器症状が①診断の6ヵ月以上前から存在、②最近の3ヵ月はそれぞれの診断基準を満たし、③症状の誘因となる器質的な病変がない、病態を機能性消化管疾患(以下、FGIDs)と定義されています。
頻繁に下痢や便秘を繰り返す過敏性腸症候群(以下、IBS)はFGIDsの一つで、腹痛により三次医療機関に紹介され、器質的疾患を否定された107名の小児の主症状をRome-Ⅱ基準で検討した結果、IBSが45%、これ以外のFGIDsの総計で23%の患者が該当することが報告されています。
急性期は症状の訴えが強く、かつ片頭痛や緊張型頭痛、心因性発熱、起立性調節障害など他の機能的疾患の合併も多くみられ、登校困難など学習や対人交流にも影響し、家庭や課外活動でも著しく患者のADLを低下させるため、医療上重要な病態です。
治療には、正常な排便習慣の回復や食事指導・生活習慣の改善を中心に、薬物療法を併用することがありますが、いずれもエビデンスは少なく、西洋薬や漢方薬の内服を試みます。